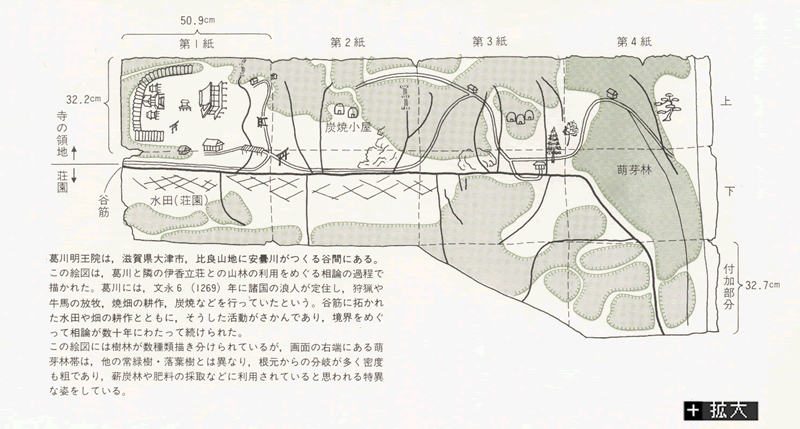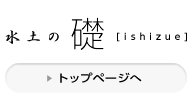農地に結びついた林野
わが国稲作の伝統的な肥料の中心は、田植え前に山野から刈り、生のまますき込む草木であった。地方によって、「かりしき」「かつちき」「ほどろ」「山のめかり」「こくさ」などとよばれるこうした草木は、田植え後に厩に入れる夏草、盆から彼岸以降に乾燥して冬に厩に入れる干草などにするため、大量に必要とされ、そのためには本田より相当広い山野が必要であった。山野は水と共に稲作を維持するための必須の資源であり、農民の関心は水と同様に山にも強く向けられていた。
すでに中世から農耕の集約化によって極限に達しつつあった里山の利用であったが、さらに元禄・享保ころ(1700年ごろ)以降、大河川の制御の進行とともに進んだ沖積平野の開発に伴い、また小農が自立していく過程で利用者が激増した。そのため、従来未利用であった奥山や藩有林野までもが利用され、村の内部での入会や、村同士での複雑な村々入会が成立した熊澤蕃山らが新田開発の抑制を唱えたのは、過度の林野利用が治山・治水の面で、耕地に悪影響をおよぼすことを危倶したからでもあった。
村々の利用権の争いが激化するとともに、村内での採草地利用の規制も強まり、利用期間の制限、草刈り用具や方法の制限による利用量の統制、刈った草の他村や他人への売買禁止が課せられた。村役人の触によって定められた日に山の口が開けら札5月上旬第1回、5月下旬第2回、田植え前の刈敷、6月下旬つくて(肥草)刈り、その後9月上旬まで厩に入れる草刈りといった作業がいっせいに行われた。こうした規制は、新しい農法を採用することへの制約にもなった。限られた水の利用をめぐって生まれた用水慣行による制約と同様の事情が、山にもあった。
こうした厳しい制約も、商品作物の栽培から導入された購入肥料の普及とともに、明治期以降しだいに緩和されていった。しかし、耕地および農民生活と林野との有機的な結びつきは強く、採草地または薪炭林などの利用により、農村の必要不可欠な構成要素として里山の雑木林があったのも、そう遠い過去のことではなく、現在の農村の景観の基礎をなしている。
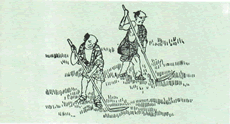
草刈り (『農具便利論』より)
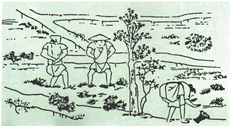
刈敷
肥料として、刈った草を田にすき込む
(『成形図説』より)
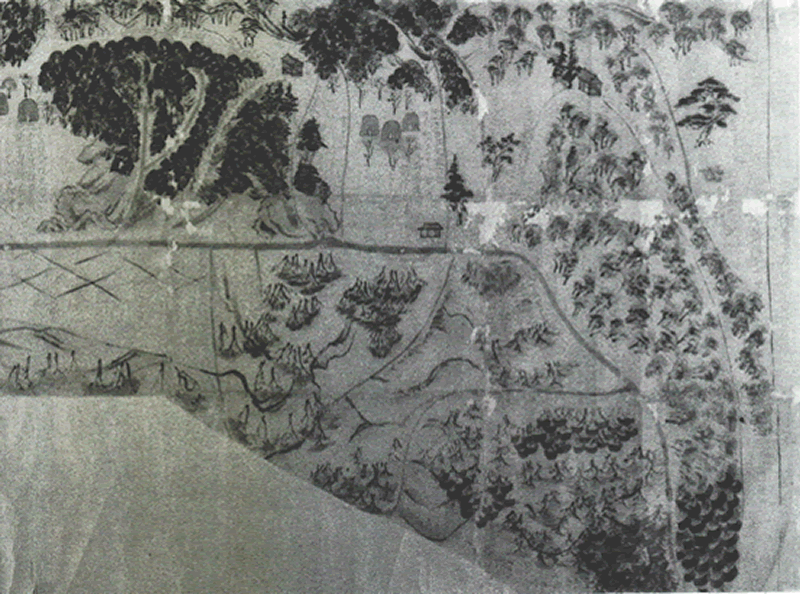
近江国葛川相論絵図
彩色絵図文保2(1318)年ごろ作成。(明王院蔵)