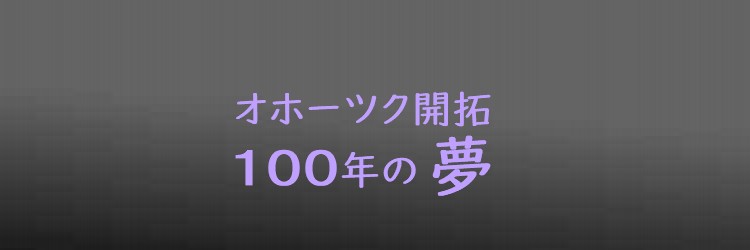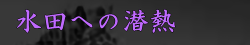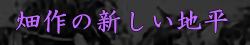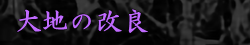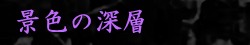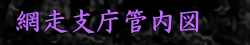第三章:燃える土

「肥料をやらなくても、5年はもつ」と勧誘の文句にあった。たしかに原生林に覆われた土地は肥沃(ひよく)に思える。事実、肥沃な土地もあった。
しかし、後に分かったことだが、北海道の耕地の多くは作物の生育には不向きな特殊土壌(泥炭度(でいたんど)、重粘土(じゅうねんど)、火山性土等)であった。この困難な土地への対応はわが国の土性調査の基礎づくりに多大な貢献をなしたとされるが、当時の入植者には関係のないことである。
人の重みで地面がブヨブヨとゆれ、また時に腰までゆかるむ泥炭地(でいたんち)※1。
乾いた泥炭層へ火が入ると、容易には消えないという。土の層そのものが燃えるのである。「畑が燃えることへの驚きと恐れ。消しても消しても、地の底から炎が立ち、主人と夢中で川からバケツで水を汲み、何十回、いや何百回も汲み、火を消しました。衣服も何も泥んこです。やっと火が完全に消えた頃、東の空が明るくなっていました。精も根も尽き果てて、ぼんやり二人で座って空を眺めていました。」
干ばつの年など、煙草の火で土の中が10日間も燃え続けたと記録にある。一度燃えた土は、雨が降っても浸透せず、風が吹けば「パフパフと飛んでしまう畑」になった。
西北の紋別地域には、重粘土層※2が多い。
戦後開拓民の凄まじい生活を描いた開口健の『ロビンソンの末裔(まつえい)』は、小説ながらルポルタージュに近いが、その一節にこうある。「・・・土でいちばん負けるのは重粘土だね。これには負ける。酸性だとかアルカリ性だとかちゅう土はいいかげんひどくても、客土するね、暗渠(あんきょ)切るね、金肥(きんぴ)撒(ま)く。そうすりゃなんとか息を吹きかえすちゅうことがあるけど、この重粘土って奴ァ、もう、どだい、作物の根が入らんのじゃけれ、またたとい根が入ったとしても息ができんのじゃけれ。」
東の斜里岳の麓にんだらかな平野が広がっている。ここは腐植(ふしょく)の少ない未熟性の火山灰地。やせ地のうえ、土が凍ると乾燥し(フリーズドライの原理)、馬車もひっくり返すという強風・斜里おろしのため今も風蝕害(ふうしょくがい)、風害が絶えない。
巨木を切り倒し、熊笹を払い、ようやく畑らしくなってきて作物を植えると、強風のため種も根も、土煙とともに作物すべて吹き飛ばされてしまう。また、防風林を植え直さねばならなかった。
世界でもトップクラスの景観美を誇る斜里の農村風景も、この防風林の整然たるたたずまい故であろう。
しかし、これらの風景は、ここに入植した開拓者達の死ぬか生きるかというギリギリの選択が形作ったものといえよう。
さて、こういう風に書き連ねるといかにも劣悪な土地のように思える。しかし、これらは、※3 多かれ少なかれ日本のいたるところで過去数千年にわたって繰り返されてきた風景ではあるまいか。
北海道、とりわけ網走地方はそれが時間的に凝縮されているだけかもしれない。
自然とはそのままでは容易に利用できないものであることを、これらの歴史は教えてくれる。
※1
湿地植物などが完全に分解されないまま堆積してできた地層。ピート、草炭とも呼ばれる。肉眼で植物組織が確認できる。亜寒帯の低湿地に多く、日本では石狩、釧路、サロベツなどに広大な泥炭地が分布する。
※2
粘土含量が高く、粘質で組織が緊密な土壌。透水性は著しく不良で乾燥時には干ばつを招きやすい。土壌が固く、耕転も困難。
※3
日本の不良土の分布は広く、畑作総面積の約半分におよぶ。主な不良土は酸性土壌、不良火山灰地、泥炭地、重粘土、礫質土など。