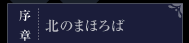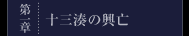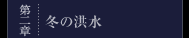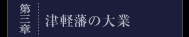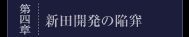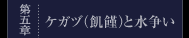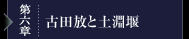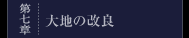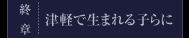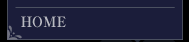稲はもともと熱帯産の植物である。
その米の栽培、主食化、そして米を中心とする社会が、古代、急速な勢いで日本列島を北上していった。そして、その北限が、津軽であった。ところが、江戸期に入り、氷期とも言われる長期的気候変動によって、この北限、つまり前述した社会的ブラキストン線は、何百キロメートルか東北地方を確実に南下したはずである。
にもかかわらず、津軽の農民はこれに耐え、命を賭けて闘い、ほとんど独力でこの社会を維持し、あまつさえ石高を飛躍的に伸ばしてきた。
津軽藩の内高[うちだか]は、宝暦[ほうれき]8年(1758)、30万5千石と公称されているが、実収は、73万石とも94万石とも推定されるらしい。
いずれにせよ、本州北限に位置する表高4万7千石の小大名が、加賀、薩摩、伊達といった大藩の収穫高と肩を並べるまでになったことになる。
この藩の新田開発高は江戸260藩中、抜きん出ている。
信じがたいことと言わねばなるまい。
津軽の新田開発は、藩直営の御蔵派立[おんくらはだち]と、民間の開発である小知行派立[こちぎょうはだち]に分けられる。
この特殊な地形を持つ平野を改造するには、御蔵派立のような大事業が必要であった。
第一に、じゃじゃ馬のような岩木川をねじ伏せるか、あるいは、もうひとつの岩木川とも言うべき巨大な用水を造らねばならない。この水浸しの平野から水を抜く排水路も必要になる。さらに旱魃[かんばつ]に備えて溜め池も築かねばならない。
江戸時代初期に建造され、350年以上を経た今も津軽平野の大動脈たり続けている、総延長16キロメートルの大用水・土淵堰[どえんぜき]。
この用水の築造や維持管理のため、津軽藩は、土淵堰奉行[ぶぎょう]という地位の高い職制[しょくせい]まで設けている。土淵堰は、この水路一本で実に約4,700ヘクタールという広大な水田を潤してきた。
また、ほとんど時期を同じくして古田放[こでんばなし]と呼ばれる長大な排水路も御蔵派立によって建設されている。ことに津軽の場合、岩木川中流から下流地帯にかけての開発は、排水路の建設によって進められたといっても過言ではない(この排水をめぐっても農民同士の複雑かつ深刻な対立を生んでいる)。
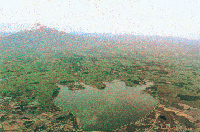
岩木山と廻堰大溜池
そして現在は津軽富士見湖と呼ばれ、秀峰岩木山を映す美しい公園に整備されている廻堰大溜池[まわりぜきおおためいけ]。
写真で分かるように、この溜め池の半分は半円状の土手でできている。土手の長さは、全国一。約6,500ヘクタールの水田へ用水を補給する津軽屈指の農業土木遺産と呼ぶべきであろう。
こうした藩直営の御蔵派立でも、せいぜい10万石程度の増加にしかならない。つまり、それ以上の開発が、村々の民百姓による小知行派立によってなされたことになる。
しかし、津軽平野の開発は、17世紀末、すでに限界に達したらしい。
その後、小規模な開発はあったものの、ほとんどが洪水等による荒廃田[こうはいでん]の復旧、用水路・排水路の修復や改良に費やされた。

乳切り田
新田開発は、さらに岩木川の最下流、現在の車力[しゃりき]村、中里[なかさと]町、稲垣村といった十三湖近くの低湿地へも進められていった。
この地域は勾配がほぼ20,000分の1。十三湖の水位によって川が逆流するので馬鹿川と名付けられた川もあったらしい。
当然のことながら、極端な排水不良田である。水が腰まで浸かれば「腰切り田」、胸まで浸[つ]かれば「乳切り田」と呼ばれた。
昭和の世まで、写真のような凄まじい光景が農作業の日常であったという。「中掻[なかが]きの頃は日照りで水不足になることが多かったので、朝2時、3時ごろ水車に上がり、足で踏んで水掻[か]きしました。」*1田植えの後は血の小便が出たと、まだ現役の老農夫はその過酷[かこく]さを語っている。
洪水、渇水、ヤマセによる凶作、そして、厳しい農作業に加え土木普請[ふしん]の苦役。

足踏み水車、大正時代、三好村、山上笙介編「五所川原」(津軽書房)より転載
津軽藩のその類を見ない開発高は、なんとも形容しがたいほどの過酷な労働と、ほとんど類を見ないほど強靭[きょうじん]な農民の忍耐によって支えられてきたのでる。
ともあれ、弥生型社会の建設、大地の改良というものがいかに困難な仕事であったか、この地の歴史は教えてくれるのではなかろうか。
※1
『新きづくり風土記』木造町老人クラブ連合会