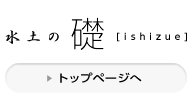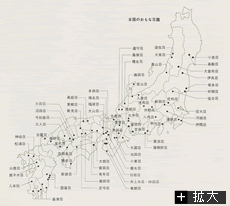国土づくりが地域に応じて進められた時代
武士の支配
建久3(1192)年、源頼朝は、貴族階級に代わって鎌倉に幕府を開いた。ここに中世封建社会の幕が切って落とされた。
しかし、鎌倉幕府の成立後も、土地制度は、荘園制度に依存し、それを利用したものであった。武士階級は、自らの手で未開の東国の土地を拓くとともに、地方の貴族から荘園の領有権を奪って、勢力の拡大を図り、新しい支配階級として成長していった。
幕府が成立すると、警察権をも手にした守護・地頭職の設置によって、荘園領主の実力は抑制された。室町期に入ると、守護が権力をもち、収納権や段銭賦課の権限を駆使して大名化し、在地の土豪と主従関係を結んだ。このため、旧来のままの荘園的秩序は重大な打撃を受けた。
応仁の乱(1467~77年)で、幕府は有名無実となる。代わって各地の土豪や国人の勢力が強まり、辺境遠国の荘園はほとんど不知行の荘園となり、武士に押領され、荘園制は崩壊していった。戦国期の到来である。自領の特徴を熟知・把握していた土豪や国人の中で有力なものは、武士と崩れゆく荘園体制を利用して、自らの領国体制を確立し、戦国大名としての地位を固めていった。一方、井堰などかんがい施設の建設と維持や、村を守るためにも、農民は団結して惣とよばれる集団をつくった。
このような時代にあって、各地では着々と開発と富の蓄積が進められ、来る時代への底力が蓄えられたのである。
大開墾の時代
従来、中世社会には大規模な開発が行われなかったといわれてきた。しかし、平安後期以降鎌倉期が在地領主層による「大開墾の時代」であったことが近年明らかになってきている。
中世における開発が停滞的であった論拠として指摘されるのは、10世紀初頭といわれる『和名類聚抄』や室町中期成立の『拾芥抄』という書物に記されている諸国田数である。10世紀から14世紀まで約400年間で、わずか8万4,000町歩(約10万ha)の増加にすぎず、その後の新田開発を含めた増加率と比べると明らかに停滞しているとされる。しかしながら、『拾芥抄』の面積が室町当時ではなく、平安末期にまでさかのぼり、年貢徴収の必要から固定した面積であって、ただちに実際の田数を示すものではないことが明らかになっている。また、畑地が全く含まれていないのである。
中世においても、各地で開発が行われており、開発の形態としては、領主的な大規模開発と農民層による小規模開発の二つの形態があったといわれる。前者は、公田の荒廃などによって財政的危機におちいっていた国衙が、在地領主層の私領開発を承認し、その力を積極的に利用しながら公田の再開発を企てようという開発奨励策の一つであった。後者は、池などのかんがい施設を築造し維持するための、村落共同体的な開発であった。
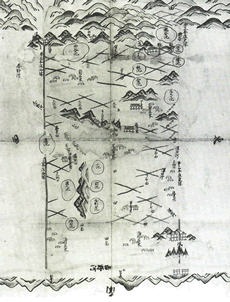
紀伊国井上本荘絵図
山麓の大きな谷池と数々の小さな皿池でかんがいされる中世の水田景観である。南東部には低湿なフケ田、南端には田畠(水掛かりの悪い不安定耕地)がある。(随心院蔵)
開発の対象も多様であり、水田の開発といってもまったくの山野を開拓するのではなく、過去に耕地化されたが荒廃している公田や、すでに耕作されている畑地の再開発であったこともある。また、畑地としての開発が主として農民により進められ、自然堤防を代表とする微高地などの水田にならない場所が、まとまった畑作地となった。山間の谷地田が造成され、また条里地割内部の不安定耕地の克服が進められていった。
こうして、畿内とその周辺地域では、前代までは手が付けられていなかった扇状地、河川の氾濫原あるいは段丘、三角州の新しい先端部などが部分的に開拓された。辺境地域では、荘園による小規模な土地所有が行われなかったため、耕地の開発が括発に行われた。特に鎌倉期の関東地方の開拓が顕著である。
農業の集約化
このような領国体制が整えられ、各地で開発が進められたこの時代の農業の特色は、集約化である。農民層の畑地に対する積極的な取り組みは、水田開発の基礎となった。山林原野はすぐ田畑化できたわけはなく、恒常的な畑地(常畑)になる前に焼畑を行うなど、さまざまな工夫がなされた。また、畑地では二毛作を行うなど集約的な利用も行われ、この経験を生かしての水田の裏作(麦の栽培)を行い、水田二毛作も行われていくのである。さらに、畑作の発展は商品作物の栽培を促し、市場流通が行われるようになった。
稲作では、この時代から田植え農法が普及した。田植え作業の前には苗代づくりのほか、牛による犁起こし、代掻きが行われ、草肥も使われた。田植えは数十人の早乙女が並び立って、音楽(田楽)に合わせて行う風景もみられた。早・中・晩稲の各品種が導入されるようになったのも、この時代からである。このほか、引板や鳴子・案山子によって収穫直前の、鳥獣を追い、稲刈りが行われた。また、脱穀作業が独立の作業となり、籾は木の摺臼を用いて玄米にされ、できた玄米は俵で納められた。これらの稲作体系は、現在の原型をなすものである。
こうして農業経営は、溜池や小河川を水源とした集約的な用水の管理や水車の使用、牛馬などの畜力の利用、施肥、二毛作、疏菜など換金作物の導入などによって、生産力を高めていった。このような発展は、西日本、特に畿内地方とその周辺で著しかった。一方、東日本の大規模な沖積平野は、まだ人口も少なく、大河川が氾濫の猛威をふるっていたため、当時の技術と資本力では開拓は困難であった。