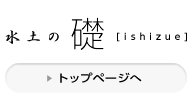中世のむら
進む集村化
奈良期から、平安期半ば過ぎにかけての集落は1~10戸未満の屋敷が三々五々展開する小村あるいは少々規模が大きくても屋敷が耕地を介在して雑然とまとまった形をとるのが一般的であった。こうした状況から、一歩現在の様子に近づくような変化をみせたのが中世であった。
畿内および周辺の沖積平野においては、平安末期から室町期までに、屋敷が1か所に集中するようになり、なかには周囲に濠をめぐらせた防御的な色彩の強い環濠集落も出現した。平野全面に広がる条里地割の中でまだまだ不安定であった水田の作付けが安定し、その面積も拡大したのであったが、耕地開発を進めるに際して、水利用の精密化や溜池の築造を行うため、むらの連帯が必要となったのである。また、開発の進展と前後して領主層の荘園に対する支配が強まり、荘域が縮まって荘内ではほぼ均等な名の編成が進んだ。さらには南北朝以後、京を中心とした戦乱に対して自衛の必要が出てきた。こうした一連の動きが、集村化の背景である。
尾張や越前などでは、遅くとも近世には集村化したが、その時期は畿内ほど早くなく、屋敷の密集度合いもやや低い。畿内と同様の社会・経済的条件に加えて、ここでは広く分布する小高い自然堤防上に洪水からの防御を意図して集落が立地することが必要であり、後背湿地を中心に条里地割が断続的に分布するのが、この地域の景観であった。

一方、大井川・庄川・天竜川などの大扇状地においては、開発が、表土の比較的厚いところや築堤して洪水を防いだところだけで分散的であり、集落もまとまってはいない。このため、近世になって開発が扇状地全面に拡大しても、散村となった。
こうした動向のほかに、中世起源の集落として豪族屋敷村が成立した。これは、樹林に囲まれた開発領主の屋敷を中心に隷属民や一般農民の家屋を従えた形をもっており、国境防衛や交通・経済の要衝を占める地点に立地していることから、小地域の中心地もしくは開発拠点となり、後の城下町のルーツとなるものとされている。

環濠集落
↑奈良県大和郡山市稗田に残る遺構
二毛作と牛馬耕
中世の農業生産の発展は、集約化という形をとったが、二毛作はその代表的なものである。文永元(1264)年、備後・備前両国の条令に、百姓が稲刈り後に蒔く麦(田麦)に対して領主が年貢を課すことを禁じたものがある。これより十数年後、紀州の高野山領では田麦にする年貢取分の史料がある。これらのことから畿内を中心にこの当時すでに二毛作が行われていたことが知られる。
室町初期には、来朝した李氏朝鮮の使者が三毛作におどろいている。また、13~14世紀ごろから1枚の田の中で盛土または地下げをしてつくる島畑が出現し、田畑ともに有効に利用するきわめて集約的な土地利用が行われていた。
こうした集約化の背景には、かんがい施設や耕耘用具の改善とともに、肥料の多用がある。平安期の史料に灌木を焼いた灰があり、鎌倉期には疏菜産地の山城・大和などで人糞尿もしくは厩肥が現れるが、肥料の主体は草肥であり、草刈り場が重要となって争議が多発する。
畑作は、農民の日常生活を支えるものであり、山畑や焼畑で営々と自家用の食物がつくられてきた。中世には、米は畿内・北陸・瀬戸内海沿岸・九州では多いが、東国では米ではなく、絹や布を年貢として出していたらしい。各地で特産物化してくるものもあり、江戸期に全面開花する商品作物栽培の素地が形成されてくる。
一方、農具の発達はあまりみられなかったのではあるが、和歌や物語によって牛馬耕(犂耕)が登場することが知られる。「すく」という言葉で田の耕起を表わしたもの、「からすき」の語が直接出てくるものがある。かつては、国司・郡司・寺社など貴族や土豪が1人で百に余る鍬や数十頭の牛馬を持っており、農民はかれらの農具で荘園の耕作をさせられていたのであるが、中世には犂耕は荘園農民の手に移り、自らの農具によって耕作し、領主の使役に応じるようになったのであろう。
わが国で伝統的に普及したのは、犂の最下部の地面に接する部分(犂床)の長い長床犂である。家族を労働力とする小農の水稲生産には、深耕に適する鍬が特に近世以降発達したが、中世においては多数の下人・奉公人を抱える地主による手作り的経営であったので、単純協業により能率を高める犂耕が適していた。

牛馬耕
(東大史料編纂所蔵『老農夜話』より)

二毛作・麦の中に綿をまく図
(『綿圃要務』より)
水の信仰
水田稲作を中心にしてきたわが国では、水にまつわる信仰や祭りが各地にあって、水とのかかわりの強さをしのばせている。湧水地点や沢水のほとり、用水の取り入れ口などに祠があり、命の水を司る水神を祀っているほか、河川堤防のかつての破壊箇所なども同じく神の坐すところとなっている。木曽三川の分流に当たった平田靱負を祀る治水神社も同じ系列のものである。いわれや形・規模などさまざまであるが、水の信仰は今でも根強い。
井堰や水路が続々と生まれるとともに神が生々しく息づいていた中世には、荘園鎮守の神がむら人の結合の証となった。家々で祀ってきた屋敷神がむらの氏神となって祀られた。田遊びや御田神事はこの鎮守神の祭りとしてはじまったといわれている。
数多く描かれた荘園絵図には神社があるが、和泉国日根荘(大阪府)絵図には、大井堰大明神、溝口大明神の二つが描かれ、河川からの取水が行われ、取水の施設が荘園の命であることを表わしている。境内に中世起源の水路を持つ大井堰や溝口の神は、水を守り、田を守り、したがって荘園を守るものとなっていたのであろう。祭りを支えたのは、井堰や水路を利用し、普請を施してきた人々であった。
また、利根川や筑後川など大河の沿岸には、河童伝承が広くみられる。筑後川流域では、平清盛の妻二位ノ尼を祀る久留米の水天宮、清盛入道の化身で河童の総大将である巨瀬川の巨瀬入道や、駅前に河童像を置く田主丸町の水神水罔像命などをはじめとして数々の伝説が残る。
水とのかかわりの強い筑後平野でも、本川から水が引かれたのは袋野・大石・山田・恵利の4堰がつくられた江戸初期のことである。筑後川は水位が低く、目の前にあっても利用が困難であり、大工事を要するため、着手できずにいたのである。大石堰の工事に当たり、失敗すれば自ら磔の刑になることを覚悟した5人の庄屋が、吉井町長野の水神社に祀られた。このような水神社は各地にあり、近くは明治用水の完成を機に建立された明治川神社(愛知県安城市)が名高い。

水神をまつる
(愛知県津島市のオミヨシサン)

河童伝承 河童伝承
(豊後の河太郎『日本山海名物図会』より)