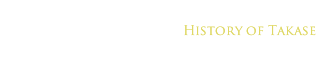

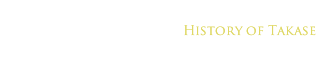

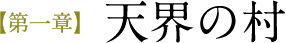

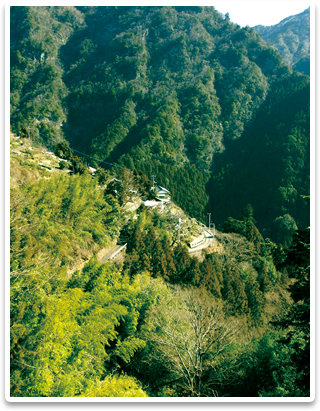
秘境中の秘境と言われる椿山集落。かつては40戸ほどあったが、ここもまた全村民が平家の末裔であるという。安徳帝を奉護する平知盛、敦盛、時子など総勢約80名が3年の歳月を過ごしたところらしい。
都集落と同じように安徳帝、武将、公達の霊を慰める「あやの踊り」「さんばれ」「敦盛踊り」「御所踊り」などからなる「椿山太鼓踊り」が毎年古式通りに奉納されている。
この村は、昭和の初期まで他の村との交流もなく、焼畑農業による自給自足の暮らしを続けてきた。
国の山々には、祖谷山や横倉山の安徳天皇陵*1をはじめ、そこかしこに平家の落人が拓いたとされる郷がある。落人の遺品や地名、あるいはこれにまつわる古老の話は、伝承ながら生々しい色彩を放っている。
伝承は平家にとどまらない。剣山の中腹に中世から居を構える三木家(徳島県美馬市)。この家は日本書紀の神代編に登場する阿波忌部氏*2の直系の子孫であり、約2千年におよぶ血筋を繋いできたという。現当主の三木氏は、古代からの役職どおり平成の大嘗祭においても麁服(麻織物)献上の大任を果たしている。
吉野川の最奥部にある高知県大川村は、「四国第一の深山幽谷なり、昔は土佐にもあらず、伊予へもつかず、阿波へも党せず、筒井、和田、伊東、山中、大薮の五党この郷をわけてつかさどる*3」と小さな独立共和国であったことが記されている。筒井とは筒井順慶の末裔らしく、同村の筒井家には順慶に宛てた信長の朱印状が保存されている。近くにも筒井家の正統があり、由緒ある太刀や鎧などを持っているという。隣の集落には、真田幸村の後裔、また、南北朝で敗れた新田氏の流れをくむ家もあるらしい*4。
そのほか例を挙げればキリがない。四国の山奥には、武田勝頼、大野治長、南朝系の山岳武士などにまつわる伝承に彩られた数多くの小さな集落が山頂近くから谷川近くまであちこちに点在している。
彼らは、平地から山奥へ移り住んだわけではなく、山の尾根から降りてきて集落を拓いた。
つまり、土佐の急峻な山々の中腹におびただしく散在するこれらの集落は、山の尾根、いわば天界から拓けてきたのである。

*1 安徳天皇陵は山口県下関市の赤間神社の御陵とされているが、宮内庁は、他にも鳥取県国府町、長崎県の対馬厳原町、鹿児島県の硫黄島、山口県豊浦郡豊田町の御陵、そして、高知県越知町の横倉山陵墓を「御陵参考地」として管理している。安徳帝の死を証明する史実はなく、生存伝説は全国数十カ所に残されている。
*2 忌部氏とは、大和政権で宮廷の祭祀などを司った古代豪族。大嘗祭においては木綿・麻布などを朝廷に貢上する役目でもあった。やがて忌部氏は阿波を拓いて阿波忌部氏を興し、さらに房総半島へ渡って安房も拓いたとされる。
*3 『寺川郷談』(1752年)
*4 『高知県史』(昭和43年)
※ページ上部イメージ写真:仁淀川町 都踊り