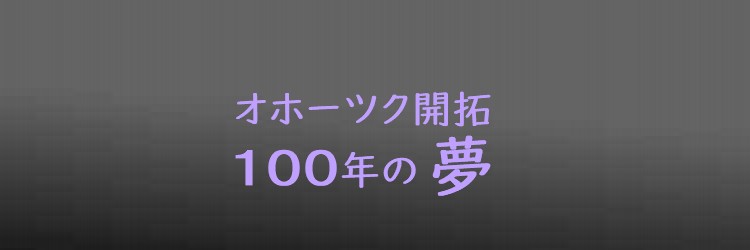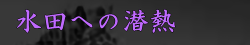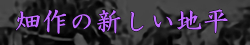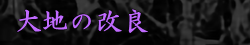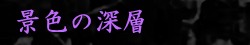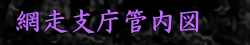第五章:畑作の新しい地平
畑作-畠作とも書く。古くは”畑”は焼畑を指し、通常の”畠”とは区別されていた。ともに国字であるが、畠は文字通り白田(はくでん)、つまり、水の張っていない田を意味している。この場合の”白”は、わずかながらニュアンスとして”劣”の意を含んでいる※1。

現在も畑は国内の耕地の半分近くを占めるが、日本では古代の班田制(はんでんせい)から近代の石高制(こくだかせい)まで基本的には租税の対象が水田であったため、畑は農家の自給用※2、ないしは桑や藍(あい)などの換金作物として、いわば副次的な扱いを受けてきた。
水田にできないよころが畑地として残った、といえば乱暴に過ぎるだろうか。いずれにせよ、畑は世界では耕地の9割を占めながら、わが国の農業においては著しく地位が低かった。
農業イコール食料と思われがちだが、そうばかりでもない。麻や綿、桑(養蚕)などの衣料、藍やベニバナの染料、他に漆(うるし)(塗料)、楮(こうぞ)(紙)、煙草、様々な薬草・・・いずれも畑作であり、中には木綿(もめん)や生糸(きいと)など日本の産業構造を変えた作物もある。しかし、これらは加工を要するため、結果的に商工業資本と結びつかざるを得ず、土地利用よりも商品相場の強い煽(あお)りを食うことになった。
流通の発達とともに、農業の投機性が芽生えてくる。
とりわけ、北海道は近年の開拓であるためその傾向が強く、官業による試作奨励とそれを支える農産物買上げ制度が拍車をかけた。
しかし、網走はあまりに遠い。道路も悪く、馬による輸送では他所(よそ)に太刀打ちできない。
ある農民が、ハッカ※3に目をつけた。加工して油の段階で売れば容量が圧縮でき、収入は他作物の10倍に近い。すぐさま大地はハッカの匂いで充満することとなった。明治末期、すでにこの地は全国の65%を占めるハッカの生産地となっている。当時、ハッカは国際市場にも進出し、やがて網走地方は世界の生産地にまで成長。ハッカ成金なる言葉も生んだ。
第1次世界大戦による農産物価格の高騰により、今度は豆成金が登場。大正6年には、馬鈴薯(ばれいしょ)のでんぷん工場がピーク。同9年、製麻業も空前の活況を呈する。市場をにらみながら、年ごと、地区ごと、作物の色が一色に塗り替えられていった。そして、水田の過激な広大と撤退。
いや、農業ばかりではない。この時期の北海道は、石炭や鉱物資源、森林資源、ニシンなどの漁業、いずれも投機的、収奪的雰囲気がみなぎっている。
畑は有機物の分解が早い。栄養分は作物に吸収される一方で、雨水とともに流亡(りゅうぼう)しやすい。地道(じみち)な土づくりを怠って収穫を続ければ、地力が減退し、やがて不毛の地と化す。
略奪的な土地利用は、古代文明衰退における大きな要因のひとつとも考えられている。
こうした事態を避けるために、外国の畑作地帯では古くからそれぞれの国に応じた土地利用、農法が発達してきた。しかし、日本では上述したように畑作を主体とした大規模な土地利用型農業は未熟であり、(耕地が狭いこともあって)畜力の利用すら未発達であった。
土地利用とは、人間と土地(環境)との相互関係性といってもいい。開拓者は当初、圧倒的な自然の営みの前に容赦(ようしゃ)なく叩きのめされた。しかし、人間が増え、人力でそれを制御できる段階になると、今度は自然に対して無制限な収奪を続けるようになる。そして歳月を経て、再び土地(環境)から強烈なしっぺ返しを受ける。
この環境をめぐる今日的課題は、早い時期から北海道で指摘されつづけてきた。
農業に関していえば、冷害など、重度なる自然災害を克服する過程の中で水田偏重の農業経営を見直し、輪作や有機物循環による持続的土地利用体系を基本とした寒冷地型畑作農業への新しい地平を築くことであった。
第2次大戦後、総合開発の対象として北海道が再度見直され、北海道開発庁および開発局が誕生することになる※4。
※1
”白”には様々な意味があるが、「収穫や負担がないさま」(『漢字源』といったニュアンスも含まれている。
※2
大根やネギなどの野菜は、大量に生産しても貯蔵がきかない。流通の発達していない時代においては、都市近郊以外、自給作がほとんどであった。
※3
ニホンハッカとも呼ばれる日本特産の作物。メントール含量が高い。メントールは消炎、鎮痛剤など様々な薬用効果があり、また香料や菓子にも使われる。
※4
それまでの開発は内務省所管であったが、内務省の廃止にともない独立した省庁として開発庁・開発局が新設された。